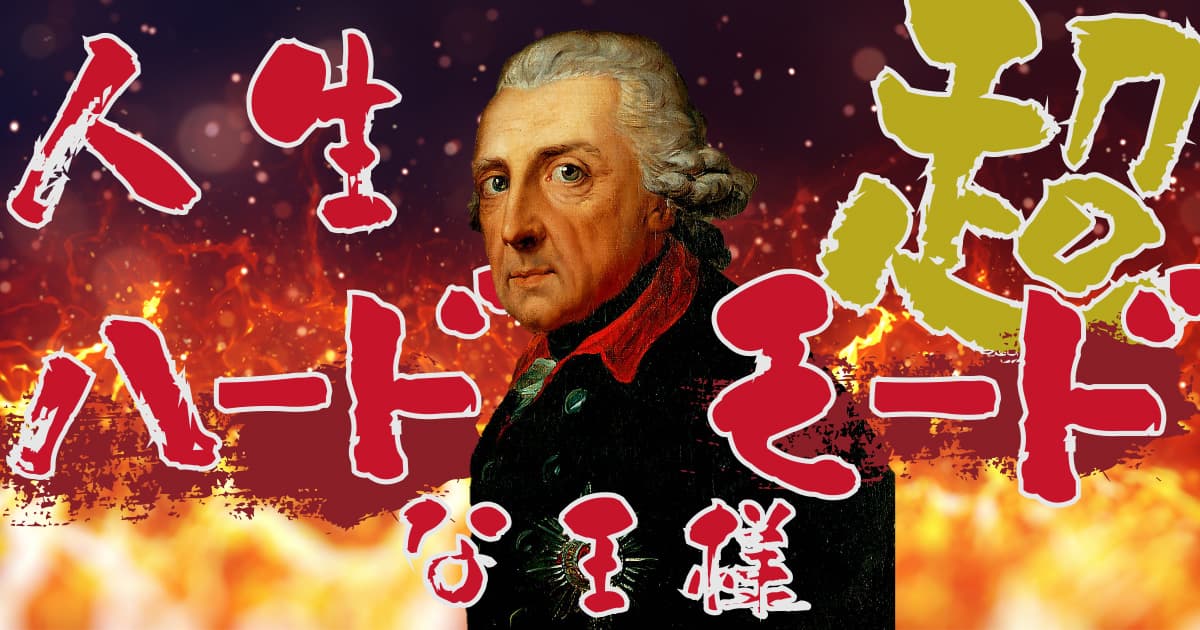
人物概要
フリードリヒ2世(1712〜1786)
フリードリヒ2世は、プロイセンを小国からヨーロッパ列強へと押し上げた「フリードリヒ大王」と呼ばれる君主です。幼少期は芸術好きでフルートを吹き、哲学や文学を愛する繊細な王子でしたが、父フリードリヒ・ヴィルヘルム1世は軍事一辺倒の“兵隊王”。真逆の気質から激しく衝突し、18歳のときには国外逃亡を試みるも失敗し、親友カッテの処刑を目の前で見せつけられるという大きな心の傷を負いました。即位後は「国家第一の下僕」を信念に掲げ、冷徹な戦略眼でオーストリアやフランス、ロシアと戦い抜き、七年戦争を生き延びます。その軍事的才能から「軍神」と称される一方で、音楽会を開き、自ら作曲やフルート演奏を楽しむ“哲人王”でもありました。さらに農政改革にも熱心で、とりわけジャガイモの普及は国を飢えから救い、いまでも彼の墓前にジャガイモが供えられています。孤独を抱えながらも最後まで国家の責務を果たした、理性と感性をあわせ持つ稀有な王でした。
ReTadoruタイプ:「戦略家 × 理想主義者 × 孤高の実践者」
フリードリッヒ二世と聞いても、ピンとくる人は多くないはずです。
ヨーロッパ史に詳しい人なら「大王(フリードリヒ大王)」といえば「ああ、あのプロイセンの軍事の天才」となるかもしれません。けれど、日本での知名度はそれほど高くありません。
けれど、この王様の人生を追ってみると、音楽を愛する繊細な王子が、父に虐げられ、親友を失い、それでも戦争と政治の修羅場を生き抜いて“軍神”と呼ばれる存在になるという、とてもドラマチックな物語が見えてきます。
個人的には「超絶ハードモードな人生だが、人生を通して啓蒙(科学的な考え方や人間の理性を大切にする考え方)を体現した」人物のように思えます。
この記事では、「フリードリッヒ二世の生涯」を、幼少期の苦悩から晩年の孤独までたどり、その中にある現代人へのヒントを探してみます。
幼少期:兵隊王の息子として生まれる
フリードリッヒ二世は1712年、プロイセン王国の王子として生まれました。
父はフリードリッヒ・ヴィルヘルム一世。「兵隊王」と呼ばれ、質実剛健・軍国主義を体現した人物です。
無駄な贅沢を嫌い、徹底的な倹約と軍事訓練を国の柱に据えた父。
対して息子のフリードリッヒは真逆でした。
- フルートを吹くことが大好き
- フランス語の本を読みふける
- 演劇や音楽を楽しむ
めっちゃ「文系の王子」ですね。
父から見れば「軟弱そのもの」。芸術は「くだらないもの」とみなされ、王子がフルートを吹いていると杖で打たれ、本を読めば没収される。
今の時代であれば全国ニュースにもなりそうな虐待を受けていました。
この時期に彼が身につけたのは、外側は従順に装いながら、内側では自分の感性を守るという二層構造。
後年の「冷静な理性の仮面の下に燃える情熱を隠す」姿勢は、この幼少期に形成されました。
青年期の大事件:逃亡と親友の処刑
18歳になったフリードリッヒは、ついに父の抑圧に耐えかね国外逃亡を計画します。
共犯は親友で近衛将校のハンス・ヘルマン・フォン・カッテ。
しかし計画は失敗。捕らえられたフリードリッヒは死刑寸前まで追い込まれ、カッテは代わりに死刑を言い渡されます。
しかも父王は「息子に見せしめるために」と、目の前で処刑を執行させたのです。
「カッテ、私を許してくれ!」
「殿下のためなら喜んで死にます!」
そう叫んだ直後、親友は斬首されました。フリードリッヒはその場で気を失ったと伝えられています。
処刑後、父王の命でカッテの遺体は王子の見える窓の下に一晩晒されたとも伝わり、この凄惨な経験はフリードリヒの心に一生消えぬ傷痕を残しました。
生き延びるには父に屈服するほかないと悟ったフリードリヒは、涙を飲んで父に謝罪の手紙を書き、全面的に恭順の意を示します。
これにより彼は処刑や廃嫡を免れ、幽閉状態から解放されました。
もっとも、自由の代償として今度は僻地キュストリンでの単調な行政実務に従事させられ、軍隊の階級も剥奪されてしまいます。
己の運命を受け入れ耐え忍ぶしかない日々…。
こうした若き日の苛烈な体験が彼の人格に与えた影響は計り知れません。
束の間の自由と才能開花:ラインスベルク城の日々
奇跡的に命を拾ったフリードリヒは、その後しばらくは父王の意向に従順に振る舞いました。
1733年、父の命令でブランズウィック=ベヴェルン公女エリーザベト・クリスティーネと結婚します。
妻となった公女は美しく教養豊かな女性でしたが、フリードリヒが彼女に心を向けることはついになく、夫婦関係は名ばかりのもので終わります。
彼女は懸命に夫の歓心を買おうと努力しましたが報われず、二人の間に子供も生まれませんでした。
即位後には別居状態となり、7年戦争終結後に数年ぶりに対面した際、彼がかけた言葉は「少し太られましたね」ただ一言だったと伝えられます。
それでも彼女は終生フリードリヒを尊敬し続け、文通は続けたといいます。
愛情には恵まれませんでしたが、この政略結婚によって父王から一定の信頼を取り戻したフリードリヒは、与えられた地方の居城ラインスベルクでようやく自由な時間を得ることになります。
ここで彼は
- 音楽仲間を招き、フルートを演奏
- 演劇やディスカッションを楽しみ
- 哲学書を読み漁る
と、自分の世界を取り戻しました。
ラインスベルクでの自由な生活はフリードリヒにとって「人生で最も幸福な時期」だったと後に振り返られています。
この時期に書かれた『反マキャヴェリ論』は、若きフリードリッヒの理想主義を象徴する一冊です。
「君主は人民の幸福を第一に考えるべき」という、当時としてはきわめて進歩的な主張でした。
王としての転機:理想から現実へ
740年5月、長年対立し続けた父フリードリヒ・ヴィルヘルム1世が崩御し、28歳のフリードリヒ2世がプロイセン王として即位します。
彼は死に際の父と和解し、「厳格だが有能な君主であった」と父を評価する言葉さえ残しました。
虐待されたり親友を殺されたり、普通であれば恨みが爆発してもおかしくはないのではと思ってしまうのですが、君主としての父を理性で評価するあたりが、個人的にはフリードリヒ2世の特性を表しているきがしてなりません。
啓蒙っぷり(感情を排して理性で思考してる感じ)がすごい。
そして即位した直後にオーストリア継承戦争が勃発。
啓蒙思想家として平和と道徳を説いていたにもかかわらず、すぐさま隣国オーストリア領シュレージエンに侵攻しました。
見事な手のひらの返っぷりに、彼を「理想主義者」と見ていた人々からすると、「結局やることは戦争か」との落胆もありました。
王になったことで彼の信念は「君主は国家第一の下僕である」というものに変わっていたのです。
理想だけでは国を守れない。国益のためには冷徹な決断が必要。
こうして彼は「理想」を掲げながらも、王になった途端「現実」最優先で行動します。
戦争では、素早い機動と各個撃破という戦術を駆使し、オーストリアを相手に勝利を重ねました。軍事の天才としての名声が一気に広まります。
七年戦争:負けないことの才能
最大の試練は七年戦争(1756–1763)。
オーストリア、ロシア、フランスなど大国が連合し、プロイセンは四面楚歌に。人口も兵力も圧倒的に不利でした。
それでもフリードリッヒは、
- 勝てる場所だけで戦う
- 撤退すべきときは冷静に退く
- 機動力を駆使して敵を各個撃破
というスタイルで「負けない戦い」を続けました。
しかし敵も黙ってはいませんでした。ロシア軍が東方から攻め寄せ、1759年8月のクネルスドルフの戦いでついにプロイセン軍は大敗を喫します。
一日の戦闘で精鋭部隊の半分近くを失い、フリードリヒ自身も命の危険に晒されました。
首都ベルリンの目前にまで攻め込まれ、さすがの大王も「最早これまでか」と覚悟を決め、側近宛の手紙に「甥(後継者)のために領土の一部でも守る交渉をすべきだ」と弱音を綴ったほどです。
このとき彼の懐には、自決用の小さなピストルが忍ばせてあったとも伝えられます。
しかしここで奇跡が起きます。
絶体絶命の1762年初頭、ロシアで女帝エリザヴェータが急死し、後を継いだピョートル3世は即座にプロイセンと講和、さらに援軍提供まで申し出たのです。
ピョートル3世はフリードリヒのことを尊敬していたらしい。そんなことある!?
劇的な形勢逆転に他の敵国も慌てて和平に傾き、結果プロイセンはシュレージエンを守り抜いたまま七年戦争を生き延びました。
この予想外の僥倖をフリードリヒ自身「ブランデンブルク家の奇跡」と呼んだほどです。
こうして欧州史上初めて「負けない」こと自体が勝利となった稀有な戦争が終わりました。
大国に包囲されながらも最後まで国家を滅亡させなかったフリードリヒの名声はドイツ中で不動のものとなり、人々は彼を「軍神」「近世のアキレス」と称えました。
ジャガイモ王のもう一つの顔
戦争のイメージが強いフリードリッヒですが、平時には農政改革に力を入れました。
特に有名なのがジャガイモの普及。
飢饉に強く、痩せた土地でも育つジャガイモを広めようと、彼は畑に見せかけの兵士を配置し、「これは王が守るほど貴重な作物だ」と印象づけました。
農民たちは「盗んででも育てたい」と考え、ジャガイモは次第に普及していったのです。
今でも彼の墓にはジャガイモが供えられています。
フリードリッヒ二世の生涯を象徴する、戦争と文化、そして庶民の暮らしを支える両面性を感じさせるエピソードです。
晩年:孤独と犬と責務
晩年のフリードリッヒは、多くの友を失い孤独に包まれていました。
それでも彼は毎朝早くに起き、政務をこなし続けました。
人間よりも犬を愛し、狩猟を「野蛮」として退け、グレイハウンドたちと過ごす時間を大切にしたといいます。
「人気も喝采もいらない。私は国家のしもべだ」
そう語った彼は、最後まで王の責務を放棄しませんでした。
王様といえば好き勝手に暮らしていそうなイメージですが、彼は誰よりも国家のために働きつづけたのです。
遺言は「サンスーシ宮殿で、愛犬のそばに葬ってほしい」。
この願いは死後200年以上経った1991年、ようやく叶えられました。
フリードリヒ2世の才能と価値観
ここで、ReTadoru的にフリードリヒの才能や価値観を見てみましょう。
ReTadoruでは“ついついしてしまうこと”=才能という概念で分析を行なっています。
【フリードリヒ2世の才能】
◉ 感情を隠して理性で振る舞う
父からの虐待や親友処刑のトラウマを経て、内心の情熱を隠し、冷静な理性で自分を守る癖がついた。
→ 才能名:二層思考家/冷静な仮面の操縦士
◉ 勝てる筋道を見抜いて集中する
「全部勝つ」より「ここだけは落とさない」を徹底。七年戦争でも一点突破と各個撃破で、圧倒的劣勢を耐え抜いた。
→ 才能名:選択的勝利主義者/機会ハンター
◉ 芸術や哲学に没頭してしまう
フルート演奏や作曲、ヴォルテールとの書簡など、実務の合間に必ず芸術を取り入れて心を整えていた。
→ 才能名:感性の燃料補給者/哲人プレイヤー
【フリードリヒ2世の価値観】
◉ 国家のために自分を捧げる
「君主は国家第一の下僕」という信念のもと、人気や喝采より国家の存続を優先した。
→ 才能名:国家奉仕者/責務ドリブン
◉ 虚飾より実利を重んじる
宮廷の派手な贅沢ではなく、ジャガイモ普及や農政改革のように庶民の生活を支える実利を大事にした。
→ 才能名:実利主義者/庶民目線の改革家
◉ 理想と現実を切り替えて統合したくなる
ラインスベルクで掲げた理想を胸に秘めつつ、戦場では冷徹な現実判断を下す。理想と現実を往復しながら国家を導いた。
→ 才能名:理想と現実のスイッチャー/哲人リアリスト
こうして見てみると、
- 幼い頃から好きだった芸術や哲学をずっと内側に抱えながら生きていた
- 啓蒙思想に多大な影響を受け理性で物事を考えるようになった
- 虐待により内面に抱えた感情や思考を押し殺すことができるようになった
という3点の特性によって、フリードリヒの生涯が説明できるような気がします。
フリードリッヒ二世の生涯が教えてくれること
フリードリッヒ二世の生涯は、
- 幼少期の虐待
- 親友の処刑
- 理想と現実のギャップ
- 孤独と責務
という苦悩の連続でした。
それを乗り越えられたのは、
- 幼い頃から好きだった芸術
- 多大な影響を受けた啓蒙思想
- 感情を押し殺すことができた
こうした特性をうまく使っていたからと言えるかもしれません。
現代を生きる私たちからするとあまりにかけ離れた人生ですが、
王様が超ハードモードな人生を乗り越えて国民から愛されたという事実は、勇気をもらえる事実です。
あなたはフリードリヒ2世の生涯に対して、どう感じましたか?
