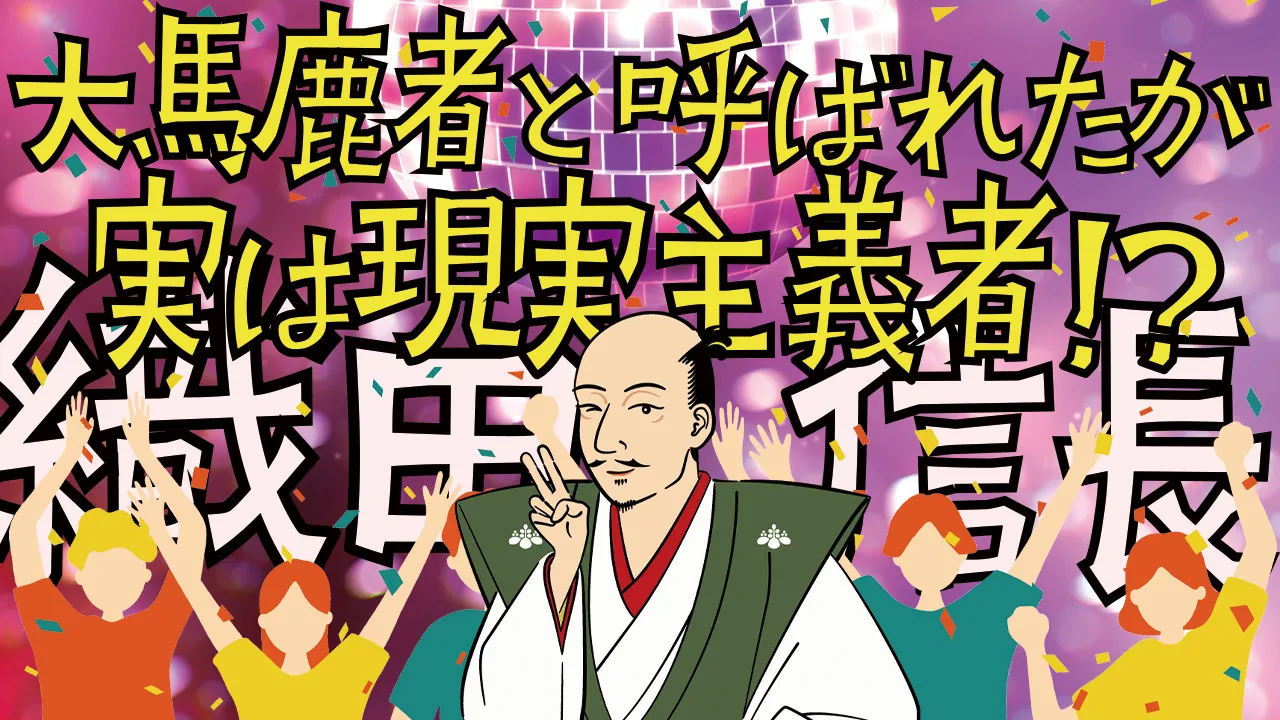
人物概要
織田信長(1534〜1582)
織田信長は、戦国の混乱を終わらせ日本統一の道筋を切り開いた革新の武将です。尾張の小大名として生まれ、若くして破天荒な行動から「うつけ者」と呼ばれましたが、その裏には常識を疑い抜く鋭い戦略眼がありました。桶狭間の戦いで今川義元を討ち天下に名を轟かせたのち、鉄砲の大量導入、楽市楽座の実施など、時代を先取りする改革を次々と実行します。一方で、比叡山焼き討ちなど非情な決断をも辞さず、その独裁的な側面は味方にも恐れられました。本能寺の変で家臣・明智光秀の謀反により倒れますが、旧来の秩序を壊して新時代を拓いたその生き方は、今もなお“革命の象徴”として語り継がれています。
ReTadoruタイプ:「革新者 × 非情な現実主義者 × 混沌の開拓者」
織田信長のことを知らない人はいないでしょう。
残虐なエピソードや豪快なエピソードが数多く伝わっていますが、その人生を改めて追ってみると、尾張の若き大うつけ(大バカ者)が、内外の闘争を生き抜いて天下統一目前まで駆け上がるという、まさにドラマチックな物語が見えてきます。
個人的には「型破りな発想と行動力で戦国の常識を破壊しつつ、現実とのバランスを取った革命児」のように思えます。
この記事では、「織田信長の生涯」を幼少期の奇行から壮年期の天下布武、そして本能寺での最期までたどり、その中にある苦悩や葛藤、そして現代人へのヒントを探してみます。
幼少期:尾張の大うつけと呼ばれて
織田信長は1534年、尾張国(現在の愛知県西部)の戦国大名・織田信秀の次男として生まれました。
幼名を吉法師(きっぽうし)といいます。
当時の尾張は室町幕府の権威が弱まり、織田家内部でも上座と下座に分かれて勢力争いをする混乱状態でした。
そんな中で生まれた信長ですが、幼少期から常識破りの行動で周囲を驚かせています。
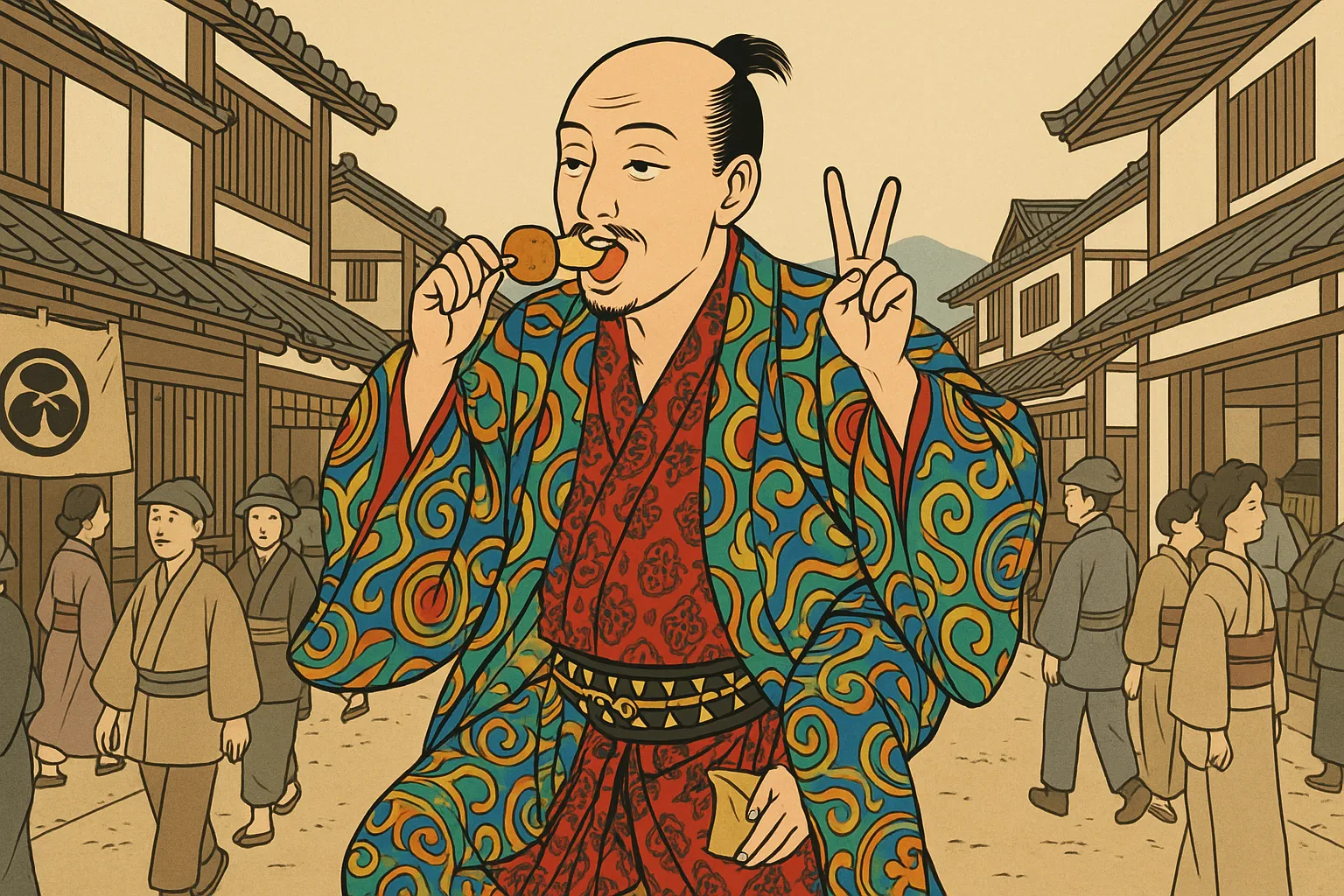
特に有名なのが、若き日の信長が「尾張の大うつけ」(尾張の大バカ者)と陰口を叩かれていた逸話です。
彼は派手好きで奇抜なファッションに身を包み、人前でも平気で食べ歩き、家臣の肩にぶら下がって歩くといった破天荒ぶりでした。
当時の身分ある若殿らしからぬ振る舞いに、周囲の大人たちは唖然。
信長本人はまったく意に介さなかったようですが、教育係の平手政秀(ひらてまさひで)は気が気でなかったでしょう。
大胆すぎる若き信長の奇抜な出で立ち(湯帷子という風呂上がり用の着物で外出し、茶筅髷というボサボサ頭、挙句に瓜をかじりながら人の肩にぶら下がるなど、常識破りの姿だったとか)。
周囲から「大うつけ」と呼ばれても本人はどこ吹く風だったようです。
父の死と仏前での非常識な振る舞い
1549年、信長は美濃国の斎藤道三の娘である濃姫(帰蝶)と政略結婚します。

しかし結婚しても彼の奇行は改まらず、政秀をはじめ周囲の心配は続いていました。
そんな中、1552年3月(諸説あり)に父・織田信秀が病没します。
19歳で家督を継いだ信長ですが、ここでも彼の非常識ぶりが炸裂しました。
父の葬儀には300人ほどの僧侶が集まり盛大に執り行われました。
ところが信長は長い太刀に脇差を藁縄で巻き付け、ちゃんと袴も履かないラフな格好で現れます。
髪型はお馴染みのボサボサ頭(茶筅髷)で、まるで風呂上がりの浴衣姿に刀を持ったような出で立ち。
もうこの時点で周囲はドン引きです。
対照的に弟の織田信行(のぶゆき)は礼装で真面目に参列しており、余計に信長の異様さが目立ちました。
そして焼香の場で、信長はいきなり抹香(香炉の粉)をワシ掴みにすると、それを仏前にバーン!と投げつけ、そのまま葬儀の席を去ってしまったのです。
唖然とする参列者が目に浮かびます。
しかし信長の型破りな言動には、家庭環境も影響していたと言われます。
信長の母・土田御前は弟の信行(信長の弟)を溺愛し、信長には冷淡だったとも伝わっており、充分な母の愛情を得られず育ったことが、若き信長の反抗的で奇妙な行動の一因だったとも考える説もあります。
教育係の切腹と若き当主の葛藤
信長の大うつけぶりに心を痛めていた教育係の平手政秀は、なんと父の死からわずか一年後の1553年、切腹して果てました。
政秀が命を絶った理由も諸説ありますが、その一つに「信長の素行が悪すぎるのを諫めるため、自らの死をもって覚悟を示した」という説があります。
自分の命と引き換えに教え子を更生させようとは、なんとも凄まじい覚悟ですよね。
実際その真偽は不明ながら、政秀ほどの重臣が亡くなったことは若き信長に大きなショックを与えたことでしょう。
これら一連の出来事を経て、信長もさすがに胸に迫るものがあったのか、徐々に行動を改め始めます。
むろん相変わらず奇抜な一面はありましたが、戦国武将としての努力も怠りませんでした。
- 毎朝毎晩の馬術稽古、夏場の水練(泳ぎの訓練)に励み、弓や鉄砲の扱い、兵法の勉強にも真剣に取り組んでいた
- 槍の柄を細く長く改良してリーチと軽さを両立させるなど、戦闘の工夫も若くして考案していた
- 16歳にして鉄砲を500丁も集めていたとも
といった真面目な一面も伝わっており、
- 敵や重臣の油断を誘うために、あえて愚かに見える行動をとったという説も
- 父からはちゃんと後継者として認められていた
- 決める場ではちゃんと礼儀正しく礼節を外さないというエピソードも
といったことから計算で馬鹿を演じていたという説もあります。
当時の名将である斎藤道三のエピソードも有名で、
信長との面会前に「うつけ」が本当か家臣に密かに調べさせたところ、信長は奇抜な外見と裏腹に、領民への指示も配下の扱いも的確で隙がない。
報告を受けた道三は「愚か者を演じているだけか」と評価を改め、会見を楽しみにしたと伝わっています。
(どの程度信憑性が高いのは不明ですが、道三が信長を見て「美濃を譲りたいほどの人物」と評したということは信頼度高そう)
実際のとこは本人しかわかりませんが、「名将言行録」(めいしょうげんこうろく)という資料によると、信長のところはだいたい「勢いだけじゃなくて、観察眼・判断・合理性の化け物」みたいな描かれ方が多いそうです。
青年期の大事件:身内の反逆と桶狭間の大勝利
父の死後、織田家中は案の定ゴタつきます。
跡継ぎとなった信長に不安を覚えた重臣や親族たちが、あれこれと画策し始めたのです。
実は織田家には分家や兄弟が複数おり、信長以外にも当主になりたがる勢力がありました。
その一人が先述の弟・織田信行です。
1556年、信行は重臣の柴田勝家や林秀貞らと結託し、信長に対して謀反を起こしました(稲生の戦い)。
この時は信長が辛勝し、母や周囲の取りなしで信行を許していますが、懲りない信行は再び密かに反逆を企てたため、1557年に信長はついに弟を手にかけました。
こうして内部の反対勢力を粛清し、他の織田一門や守護代家も倒して、信長は20代半ばまでに尾張国をほぼ統一しました。
しかし彼の試練はこれで終わりません。下剋上の嵐吹き荒れる戦国時代、尾張の小大名に過ぎなかった織田信長に、今度は外部から巨大な試練が襲いかかります。
桶狭間の戦い:下剋上を体現した奇跡
1560年、駿河国の大大名・今川義元が2万以上とも言われる大軍を率いて上洛(京都に上ること)を目指し、隣国三河・尾張へ攻め込みました。
今川義元といえば東海地方一帯を治める強豪で、織田家とは比べものにならない大勢力です。
対する信長はわずか数千の兵力。
もはや今川義元は織田家のことをライバルとは思っておらず、尾張なんて通過点くらいにしか思っていなかったとも言われています。

すでに織田側の砦は次々に落とされ、普通なら籠城か降伏を選ぶしかない局面だったのですが、ここで信長は常識破りの奇策を打ちます。
大軍を迎え撃つのではなく、奇襲による本陣強襲を決断したのです。
信長は桶狭間周辺が丘に囲まれた窪地で、雨と霧で視界が悪くなる地形に着目しました。
大軍ほど情報伝達が乱れ、小軍は気付かれずに動きやすい。
さらに砦陥落の連続で、今川本陣には「勝った空気」が流れ、酒宴が開かれていたとも伝わっています。
信長はこの油断を逃さず、全兵力を一点に集中して今川義元の本陣へ突撃させたのです。
こうして1560年6月、桶狭間にて織田軍は豪雨に紛れて今川本陣を急襲し、油断していた義元の首級を挙げる大金星をあげました。
この桶狭間の戦いは、「弱者が強者を討つ」戦国史屈指のドラマとして語り継がれています。
出陣前、信長は舞を舞いながら「人間五十年、下天の内をくらぶれば夢幻の如くなり。一度生を得て滅せぬ者のあるべきか」(人の世の50年なんて、天上の時の流れから見れば夢幻のようなものだ)という敦盛の一節を口ずさんだといいます。
これにより多くの若い家臣たちが鼓舞されましたといいます。
死が身近に存在する時代の中で、「まぁ人生こんなもんよ」と開き直った瞬間なんじゃないかと個人的には感じる逸話です。
桶狭間の戦いによって弱小大名だった織田信長の名は一気に全国に轟き、この勝利を機に盟友となる徳川家康(当時は今川配下だった松平元康)とも協調関係を築きました。
桶狭間で今川義元を撃破した信長は、「時代の覇者」に向けて走り始めます。
美濃国の斎藤氏をも1567年までに攻略し、稲葉山城(岐阜城)を奪取すると、拠点を岐阜に移しました。
この時、彼は有名な「天下布武」の印判を用い始めます。
転機:京都上洛と理想と現実のはざま
1568年、信長は足利義昭(あしかが よしあき)という人物を奉じて京都へ上洛します。
義昭は室町幕府の将軍家の一人でしたが、争乱で地位を追われており、信長は彼を将軍に擁立して影響力を握ろうと考えました。
これにより信長は将軍の後ろ盾という大義名分を得て、畿内(近畿地方)に勢力を広げます。
しかし、信長と将軍義昭の関係は長くは続きませんでした。
義昭は将軍に返り咲き再び将軍中心の権力基盤を整えたいと考えていましたが、信長はそうではありませんでした。
義昭が将軍に返り咲いても、実際の権力は信長が全て握っていたのです。
義昭はやがて信長の専横ぶりに反発し、各地の大名に密書を送って「信長包囲網」を築こうと画策します。
こうして信長は次々と強敵との戦いに巻き込まれていきました。
理想に燃えて掲げた「天下布武」ですが、現実には裏切りや反発が相次ぎ、四面楚歌の状況に陥ります。
信長包囲網との戦い:試練の連続
1570年、信長は北近江の浅井長政・越前の朝倉義景連合軍と激突します(姉川の戦い)。
この時は勝利したものの、一時は窮地に追い込まれ、同年には浅井・朝倉の援軍である延暦寺の僧兵勢力に苦しめられます。
怒りに燃えた信長は1571年、比叡山延暦寺の焼き討ちを断行。
老若問わず多くの僧や人々を虐殺し、寺社勢力に恐怖を刻みつけました。
この苛烈な行動には「容赦なさすぎる…」と戦国時代の人々も震え上がったとか。
やりすぎな気はしますが、個人的には「シンプルに敵が京都を見下ろす位置に武装してたらぶっ潰すでしょ」というリアリストな性格が出てるんじゃないかと思ったりもします。

それでも敵は次から次へと現れました。
甲斐の武田信玄は「戦国最強の騎馬軍団」を率いて西上し、1572年の三方ヶ原の戦いでは盟友の徳川家康が大敗を喫しています。
武田軍の猛威にさすがの信長も苦戦必至かと思われました。
しかし翌1573年、天下の名将・信玄がまさかの急死! そんなことある!? と言いたくなる僥倖で、信長は最大の脅威から救われます。
これに勢いづいた信長は浅井・朝倉を一気に滅ぼし、反旗を翻した将軍・足利義昭も追放しました。
こうして約240年続いた室町幕府は名実ともに滅亡し、織田信長が天下人(実質的な日本の覇者)としての地位を確立したのです。
1575年には、信長の軍事的才能が遺憾なく発揮されます。
かの有名な長篠の戦いで、織田・徳川連合軍は武田勝頼の騎馬軍団を銃による集中砲火で撃破しました。
信長は自慢の鉄砲隊を三段撃ちに配置したとされ、これが戦況を大きく左右したと言われます(諸説ありますが)。
いずれにせよ、刀槍の時代に銃器の威力を見せつけた戦いであり、旧来の騎馬武者の突撃戦法を時代遅れにした革命的勝利でした。
戦国最強と恐れられた武田家も、この戦いを転機に衰退し、最終的に1582年には信長の手で滅亡します。
それでも信長の試練は終わりません。
石山本願寺(大阪)の一向一揆勢力や、中国地方の大大名毛利氏との戦いなど、全国統一への道は常に茨の道でした。
ことに一向一揆との戦いは10年に及ぶ長期戦で、信長も何度か痛い目に遭っています。
1574年の長島一向一揆攻めでは織田軍が大損害を受け、信長自らも命からがら撤退しました。
さすがの信長も「これはヤバいかも…」と弱音を漏らしたとか漏らさないとか。
それでも彼はあきらめず、勝てるときだけ戦い、劣勢なら退く冷静さでじわじわと敵を削り続けます。
そして奇跡的な幸運も味方しました。
1578年には越後の名将上杉謙信が急死し、1580年には宿敵・本願寺顕如が講和に応じて石山本願寺が開城します。
気づけば信長の周りから強敵がいなくなりつつありました。
これを信長自身、「神仏も我を助けるか」と感じたかもしれません(実際には信長は無神論者っぽいですが…)。
欧州史のフリードリヒ大王が「ブランデンブルク家の奇跡」で救われたように、信長も運までも味方につけて戦国最強への階段を駆け上がったのです。
織田信長の性格:残虐な覇者と革新的な改革者
戦場で恐れられた織田信長ですが、その一方で彼は革新的な施策を次々と打ち出した人物でもありました。
まさに「武」の顔と「治」の顔、二つの側面を持つリーダーだったのです。
信長と言えば残虐エピソードがよく取り沙汰されます。
比叡山焼き討ちに代表されるように、敵対する相手には女性や子供であろうと一切容赦しませんでした。
降伏した武将を処刑したり、一揆勢力を殲滅するために容赦なく皆殺しにするなど、その冷酷さから「第六天魔王」(仏教で最も凶悪な魔王の意)と怖れられています。
目的のためには手段を選ばないその苛烈さは、「鳴かぬなら殺してしまえホトトギス」という有名な句にも象徴されていますよね。
部下であっても無能と見れば厳しく叱責・粛清し、身内ですら反すれば切り捨てる。
その徹底した合理主義は恐ろしくもありますが、残虐だから手段を選ばないのではなく、徹底したリアリストだからこそな気がします。
しかしそんな信長にももう一つの顔があります。
それは文化人・改革者としての顔です。
彼は戦国大名の中でも特に新しいもの好きで好奇心旺盛でした。
趣味は鷹狩や相撲観戦、そして何より茶の湯(茶道)を愛しました。
天下統一の合間にも茶会を開き、名物茶器を収集したり、茶匠の千利休らと交流しています。
豪華絢爛な安土城を築いたのも信長で、天守には当時最新の南蛮(ヨーロッパ)文化や唐(中国)風の意匠を取り入れたとされます。
また、鉄砲伝来以降いち早く大量導入したり、南蛮人(ヨーロッパ人)宣教師を保護して西洋の知識や技術に触れるなど、新技術や異文化にもオープンでした。
政治・経済面でも先進的でした。
楽市楽座の政策を各地で実施し、既得権益だった座(商人の商会のようなもの)を廃止して自由な商取引を奨励しました。
城下町には商人や職人を集め、市場を開放して経済を活性化させています。
これにより民衆は商売の機会を得て潤い、信長自身も税収増でウハウハ…というWin-Winな改革でした。
当時としては斬新な経済政策ですよね。
また、身分に捉われない実力主義も打ち出しました。
農民出身の豊臣秀吉を大出世させたり、敵だった明智光秀や滝川一益を重用するなど、人材登用は割と柔軟でした。
古い家柄や権威にとらわれず、役に立つものは何でも使うという現代的なリーダー像が垣間見えます。
こうした革新的な側面を見ると、織田信長は決して破壊と殺戮だけの人ではなく、新しい時代の礎を築いた改革者でもあったとわかります。
戦で見せる魔王の顔と、治世で見せる合理主義者の顔。
相反するようでいて、徹底した現実主義のように感じます。
この現実主義によって、彼は急速に国力を高め天下統一目前まで迫れたのでしょう。
最期:天下統一目前での非業の死
1582年、織田信長はついに日本の大半を掌握し、残るは中国地方の毛利氏や関東・東北の数家を残すのみとなっていました。
息子たちや腹心の部下たちを各方面に派遣し、自らは京都の本能寺で天下統一の仕上げに向けた陣頭指揮を執っていました。
もう天下は目前、「あと一息で歴史に名を残す天下人だ!」というタイミングです。
ところが…まさかの悲劇が信長を襲います。
1582年6月2日未明、本能寺の変。
明智光秀が謀反を起こし、主君信長に牙を剥いたのです。
光秀はかつて浅井・朝倉攻めや一向一揆鎮圧などで功績を挙げた重臣でした。
信長も彼を信用し、中国攻めの援軍として派遣していた矢先の出来事です。
その光秀が突如反旗を翻し、軍勢を率いて京都の本能寺を包囲しました。
護衛も少なく不意を突かれた信長は大ピンチ!「是非もなし」と覚悟を決め、奮戦虚しく最期は自刃したと伝わります。
49歳、まさに人生これからという時に、あまりに劇的で無念な最後でした…。
どうして光秀が裏切ったのかは今なお謎が多く、諸説飛び交います。
主君からの度重なる叱責に耐えかねたとか、野望を抱いたとか、細川ガラシャ(光秀の娘)の婚約破棄事件の恨み?とか…歴史ミステリーとして語り出すとキリがありません。
ただ下剋上が当たり前の時代において、光秀の謀反も当たり前といえば当たり前な気がします。
信長の周囲には護衛が少なく、光秀は秀吉を助けるための兵を率いていました。
「今しかない!」となったのでしょうか。

本能寺で果てた信長ですが、その後の展開はご存じのとおり。
後継者争いを経て、かつての家臣で盟友でもあった羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)が天下統一を引き継ぎ、最終的には徳川家康が江戸幕府を開くことになります。
織田信長自身は天下統一を目前にして倒れましたが、その遺志と基盤はしっかり後世に引き継がれ、日本史は戦国から近世へと大きく転換していきました。
振り返ってみると、織田信長の一生は波乱万丈そのものです。
奇行と非難に満ちた青年期、命がけの戦いと勝利の快感、仲間の裏切りと家族との悲劇、そして志半ばでの壮絶な最期…。
まさしく超ハードモードな人生ですが、その中でも信長は自らの才能や価値観を武器に、この苛烈な人生を駆け抜けました。
ここで、ReTadoru的に信長の才能や価値観を分析してみましょう。
織田信長の才能と価値観
ここでは、AI自己分析アプリ「ReTadoru」の観点で織田信長という人物をひもといてみます。
ReTadoruでは「何気なくしてしまっていること」=才能という切り口で個人を分析します。
信長のエピソードから見える才能と価値観をピックアップしてみましょう。
【織田信長の才能】
◉ 大胆不敵にリスクを取ってしまう – 常識に囚われず、大勝負に出る胆力がありました。
桶狭間の奇襲や度重なる奇策など、「負けたら終わり」の局面でも怖気づかず突き進む姿勢です。
→ 才能名:勇猛果敢なリスクテイカー/電光石火の奇襲者
◉ 新しい技術やアイデアを即座に取り入れる – 南蛮から伝来した鉄砲を大量導入し戦術に活かす、城下で楽市楽座を実施して経済を活性化するなど、革新的な発想を次々実行しました。
保守的な戦国武将が多い中、流行り物に飛びつくフットワークの軽さが際立ちます。
→ 才能名:革新的トレンドハンター/時代の先取り名人
◉ 相手を徹底的に叩き潰す – 一度「倒す」と決めた相手には情け容赦なく殲滅する徹底ぶりがありました。
比叡山焼き討ちや、一向一揆の殲滅戦など、その冷酷さは恐怖政治さながら。
しかしこの非情さゆえに二度と敵が復活できなくなり、結果的に自分の支配を盤石にしています。
→ 才能名:冷酷非情のストラテジスト/恐怖のカリスマ統率者
【織田信長の価値観】
◉ 壮大なビジョンに己を捧げる – 「天下布武」を掲げ、天下統一という途方もない目標に生涯を賭けました。
自らを「第六天魔王」と名乗ることさえ辞さず、全国平定のためなら自身が悪役になることも厭わない。
その生き様からは、ビジョンのために全てを投じる信念がうかがえます。
→ 価値観名:ビジョンドリブンな革命児/野望に生きるロマン主義者
◉ 権威や伝統より実力・合理を重視 – 信長は由緒正しい将軍家ですら追放し、寺社の権威も平然と踏みにじりました。
旧来のしがらみよりも「役に立つかどうか」「勝てるかどうか」で判断するリアリストです。
身分の低い者でも功績次第で重用するなど、結果と実力を最優先しました。
→ 価値観名:実力主義の改革者/アンチ権威の合理主義者
◉ 新しい文化や知識を貪欲に受け入れる – 茶の湯や南蛮文化など、常に最新のトレンドを楽しみ吸収しました。
戦国武将でありながら芸術や外交にもセンスを発揮し、「面白そう」「役立ちそう」と思えば伝統にとらわれず採用する柔軟性がありました。
→ 価値観名:オープンマインドな好奇心家/異文化アクセプター
こうして見てみると、
- 大胆不敵な行動力(怖れを知らぬチャレンジ精神)
- 革新的な先見性(新しいものを取り入れる柔軟性)
- 冷徹な合理主義(感情より目的を優先する割り切り)
という3つの特性によって、織田信長の波乱の生涯が支えられていたように思えます。
幼い頃から型破りだった彼は、その奔放さを大胆な決断力として昇華し、未知の技術を駆使して強敵を打倒し、情に流されない冷静さで組織を束ね上げました。
この組み合わせ、現代にいたら超カリスマ経営者タイプかもしれませんね…!
織田信長の生涯が教えてくれること
織田信長の生涯は、現代の私たちから見るとスケールが違いすぎて一見遠い世界の物語です。
しかし、その中にある苦悩と克服の物語は意外と普遍的に感じられます。
信長は、
- 若い頃に周囲から理解されず批判される苦悩(「大うつけ」と蔑まれ、師を自死で失う)
- 身内や仲間に裏切られる悲劇(弟の反逆や家臣の謀反に直面)
- 理想と現実のギャップに苦しむ葛藤(天下統一の理想 vs 四面楚歌の現実)
- 成功の絶頂で孤立し命を狙われる恐怖(頂点に立ちながらも最後は本能寺の変)
といった試練の連続でした。
それでも彼が歴史に名を残す偉業を成し遂げられたのは、
- 大胆不敵な行動力(失敗を恐れず挑む勇気)
- 革新的な発想(新しい技術やルールを取り入れる柔軟さ)
- 冷徹な決断力(非情なまでに目的を貫く意志)
といった自分の特性をうまく活かしたからだと言えるでしょう。
凡人には真似できない荒業も、信長にとっては「ついやってしまう」才能の発露だったのかもしれません。
まったく規格外すぎる織田信長の人生ですが、弱冠20代の若者が逆境をものともせず戦国の世を駆け上がり、大勢の人々を動かして歴史を変えた事実は、私たちにも大きな勇気を与えてくれます。
「自分なんて」と臆してしまう時、信長の破天荒だけど信念に満ちた生き様を思い出すと、少し元気が湧いてきませんか?
あなたは織田信長の生涯から、どんなことを感じましたか?
